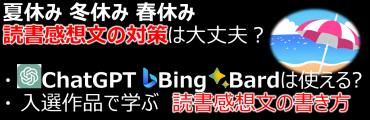明治、大正、戦前昭和に作品を著した有名な作家は、作品がどのくらい国語教科書に採用されているのでしょうか。
今でも広く知られている小説家の採用作品数を、独断でランキング形式にまとめました。各小説家の代表作は、Wikipediaの記事を参考にしています。
5位:太宰治
5位は太宰治、教科書採用数は2作品です。代表作からは「走れメロス」が採用されています。
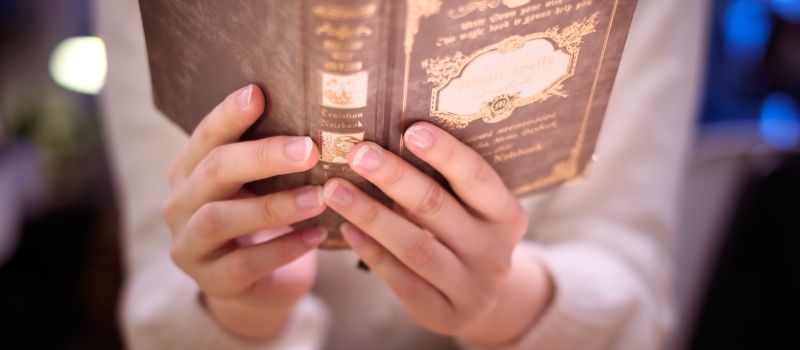
その他の主な採用作品を以下に掲載します。
・猿ヶ島
4位:森鴎外
4位は森鴎外、教科書採用数は9作品です。代表作からは「山椒大夫」「高瀬舟」が採用されています。
その他の主な採用作品を以下に掲載します。
・最後の一句
・木精
・安井夫人
3位:夏目漱石
3位は夏目漱石、教科書採用数は12作品です。代表作からは「吾輩は猫である」「坊っちゃん」「三四郎」「草枕」が採用されています。
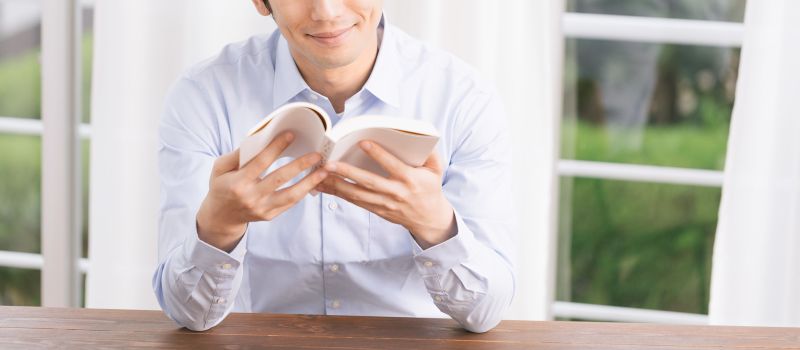
その他の主な採用作品を以下に掲載します。
・二百十日
・文鳥
・夢十夜
夏目漱石の長編小説が採用されることが多く、例えば「吾輩は猫である」なら、教科書にはその一部分のみ抜粋して掲載されます。
別々の章や節が採用された場合も元の長編小説の数に含めて数えていますので、一見すると少なく見えますが、実際にはもっと多く掲載されています。
2位:芥川龍之介
2位は芥川龍之介、教科書採用数は21作品です。代表作からは「鼻」「戯作三昧」が採用されています。
その他の主な採用作品を以下に掲載します。
・蜘蛛の糸
・トロッコ
・杜子春
・仙人
・舞踏会
・魔術
1位:宮沢賢治
1位は宮沢賢治、教科書採用数は26作品です。代表作からは「注文の多い料理店」「雨ニモマケズ」「銀河鉄道の夜」「風の又三郎」が採用されています。
宮沢賢治は細かく分類すれば童話作家に入りますが、絵本ではない童話と、短編小説の境目を決めるのは難しいため、このランキングに含めました。
その他の主な採用作品を以下に掲載します。
・オツベルと象
・グスコーブドリの伝記
・セロひきのゴーシュ
・やまなし
・雪わたり
番外
番外で、戦後昭和でも活躍した志賀直哉、井上靖を取り上げます。
この二人の作家は、国語教科書の編集・監修にも携わってきました。よって作家と作品選定者が重なると条件がフェアではないため、分けています。
志賀直哉
番外の一人目は志賀直哉、教科書採用数は30作品です。代表作からは「清兵衛と瓢箪(ひょうたん)」「城の崎にて」「小僧の神様」「暗夜行路」が採用されています。
井上靖
番外の二人目は井上靖、教科書採用数は22作品です。代表作からは「氷壁」「天平の甍(いらか)」「しろばんば」が採用されています。