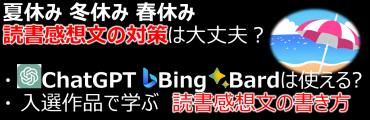小学校の国語学習につきものなのが音読です。この音読の授業で特徴的なフレーズを口ずさんだので、その後もそこだけは覚えている作品があるのではないでしょうか。
そんな【音が印象的だった、忘れられない】作品を5つ取り上げました。
やまなし(宮沢賢治)
一つめは、宮沢賢治の「やまなし」です。
やまなし、って何だったかしら、と思い出せない人もいるかもしれません。特徴的なフレーズは、
クラムボンはわらったよ
クラムボンはかぷかぷわらったよ
クラムボンははねてわらったよ
クラムボンはかぷかぷわらったよ
という冒頭の部分でした。(→「やまなし」の情報を見る)
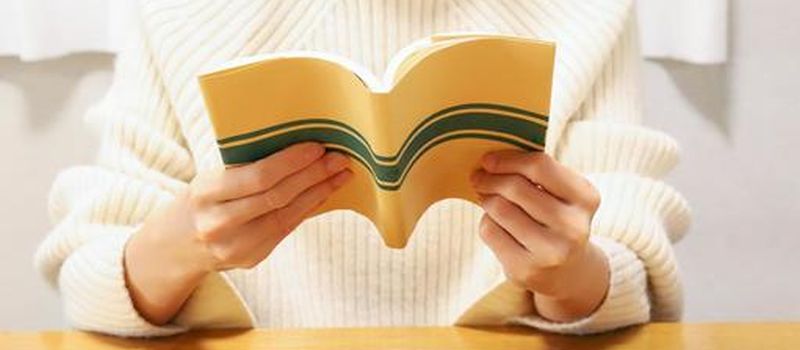
川底で暮らすカニの兄弟とお父さんのお話でした。春のシーンで、兄弟はクラムボンという何かについて話します。その後、クラムボンは死んだ、殺されたとも話します。
何か良くないことが起こったような様子ですが、それでもクラムボンという響きには悲壮感はなく、小ささやかわいらしさすら感じます。
河童と蛙(草野心平)
二つめは、草野心平の詩「河童と蛙」です。特徴的なフレーズは、
るんるん るるんぶ
るるんぶ るるん
つんつん つるんぶ
つるんぶ つるん
という、何度も繰り返される擬音語の部分でした。(→「河童と蛙」の情報を見る)
この詩では、繰り返される特徴的なフレーズのほかには、河童や周りの山、月が擬人的に描かれます。
楽しさや躍動感、滑らかさなどを表しているのでしょうか。あなたはどう思いますか。
りすのわすれもの(松谷みよ子)
三つめは、松谷みよ子の「りすのわすれもの」です。
この「りす」「わすれもの」で当時の内容を思い出せた人もいるかもしれませんね。特徴的なフレーズは、
ブッブ、ウッププー
ブップ、ウッププー
という冒頭の山鳩の鳴き声でした。(→「りすのわすれもの」の情報を見る)
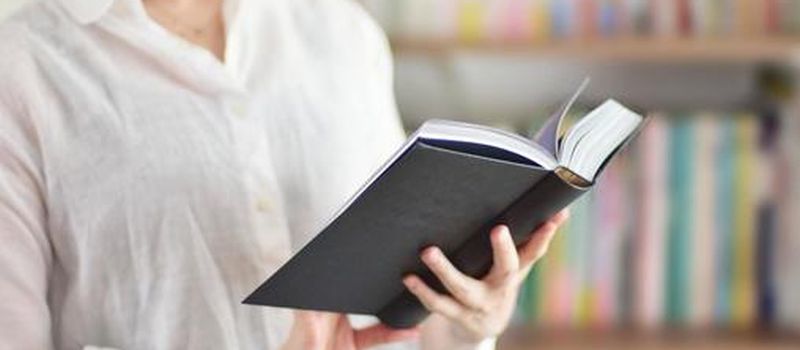
主人公のリス(名前はさんた)は、この山鳩の鳴き声で目を覚まします。そしてクルミの木にクルミをねだると、クルミの木はリスのわすれものの話をします。
本当のリスも木の実を土に埋めて隠したあげく場所を忘れてしまい、そこから芽が出て育つことがあるようですから、まったく空想の話でもないようです。
きつねのおきゃくさま(あまんきみこ)
四つめは、あまんきみこの「きつねのおきゃくさま」です。特徴的なフレーズは、
とっぴんぱらりのぷう
という、物語の終わりを締める部分でした。(→「きつねのおきゃくさま」の情報を見る)
とっぴんぱらりのぷうは秋田弁に由来する言葉のようです。秋田に多く伝わる昔ばなしを話すときには、終わり(結び)を「とっぴんぱらりのぷう」「とっぴんからりのさんしょのみ」「どっとはらえ」などで結ぶのだとか。(→「秋田県県政だより 平成13年 Vol12」より)
雨ニモマケズ(宮沢賢治)
最後の五つめは、また宮沢賢治の「雨ニモマケズ」です。
全文にわたってすべて特徴的なフレーズといってもよいくらいですが、一度口に出したら忘れられないのは、
雨ニモマケズ
風ニモマケズ
という冒頭の部分でしょう。(→「雨ニモマケズ」の情報を見る)
後半でも、「東に病気のこどもあれば」「西につかれた母あれば」「南に死にそうな人あれば」「北にけんかやそしょうがあれば」と韻を踏むフレーズがあり、頭に残っている方もいるのではないでしょうか。