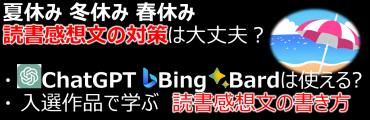戦後教科書でもっとも長く読まれている作品のトップ5をまとめました。中学校編です。
3位:故郷(魯迅)
3位は、魯迅の「故郷」です。
1953年(昭和28年)から今に至るまで、中学二年生や中学三年生で長らく読み継がれています。
主人公は久しく帰っていなかった故郷に20年ぶり帰省します。故郷の美しい記憶を抱いて戻ったものの、子供の頃の友人や知人に再会し失望する、というお話です。(→「故郷」の情報を見る)

故郷では地主階級の家の子だった主人公ですが、ある小作人の息子と仲良しでした。しかし、最後に会ってから30年ぶりに会ってみると、どうも態度がよそよそしく、記憶の中の彼とはずいぶん違います。
しかし、最後には主人公の甥っ子と彼の子どもに芽生えた友情を知り、希望を見出すのでした。
2位:トロッコ(芥川龍之介)
2位は、芥川龍之介の「トロッコ」です。
1949年(昭和24年)から今に至るまで、一度も途切れず中学一年生の教科書で読み継がれています。
当時8歳の良平は、家の近くで始まった鉄道敷設工事の現場を見に行き、そこで使われていたトロッコに興味を持つ、というお話です。(→「トロッコ」の情報を見る)
ある日、作業員と一緒にトロッコを押すチャンスが来て、喜んで一緒に押し始めます。やがて線路が下りになるとトロッコに乗って進み、嬉しくなったのでした。
しかし、押したり乗ったりしているうち、知らぬ間に遠くへ来てしまいます。幼い良平は果たして無事に帰れたのでしょうか。
1位:少年の日の思い出(ヘルマン・ヘッセ)
1位は、ヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」です。
1948年(昭和23年)から今に至るまで、主に中学一年生で長らく読み継がれています。
「私」が客に、幼年時代に熱中した蝶の収集を再開したことを告げ、収集した蝶を見せるところから物語は始まります。(→「少年の日の思い出」の情報を見る)
客は収集品を少し見るのですが、やや不愉快な気分になったらしく、見るのを止めてしまいます。そこから、その客の少年時代に起きた苦い思い出が語られます。
番外:徒然草(兼好法師)
番外の一つめは、兼好法師の「徒然草」です。
1946年(昭和21年)から今に至るまで、長らく読み継がれています。
そして、戦中・戦前でも教科書に載っているどころか、明治時代から教科書で読み継がれています。
兼好法師が思ったことや雑多な感想、聞き及んだことをつらつらと書いた随筆です。(→「徒然草」の情報を見る)

つれづれなるままに、日暮らし(ひくらし)硯(すずり)に向かひて...と書き始める序段や、52段「仁和寺にある法師」、109段「高名の木登り」が、繰り返し教科書に取り上げられています。
番外:枕草子(清少納言)
番外の二つめは、清少納言の「枕草子」です。
同じく、1946年(昭和21年)から今に至るまで、長らく読み継がれています。
そしてこちらも、戦中・戦前でも教科書に載っているどころか、明治時代から教科書で読み継がれています。
鴨長明の「方丈記」、兼好法師の「徒然草」と並び、日本三大随筆の一つとして有名です。(→「枕草子」の情報を見る)
春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこりあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる...から始まる序段の付近や、151段「うつくしきもの」が、繰り返し教科書に取り上げられています。