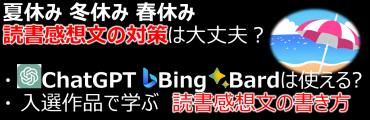国語教科書に全部が載ってない長編小説だけでなく、短編作品でも最後のストーリーが思い出せないものがありますよね。
教科書の定番作品で、結末はどうなったか思い出せない、または習っていないものを集めました。
ベンチ あのころはフリードリヒがいた(ハンス・ペーター・リヒター)
一つめは、ハンス・ペーターの「ベンチ あのころはフリードリヒがいた」です。
ナチスが第二次世界大戦に向かって突き進むドイツで暮らす僕と、友人でユダヤ人家族のフリードリヒとに起こる日常の出来事を、当時の悪化する世相を反映して描いたお話です。(→「ベンチ」の情報を見る)
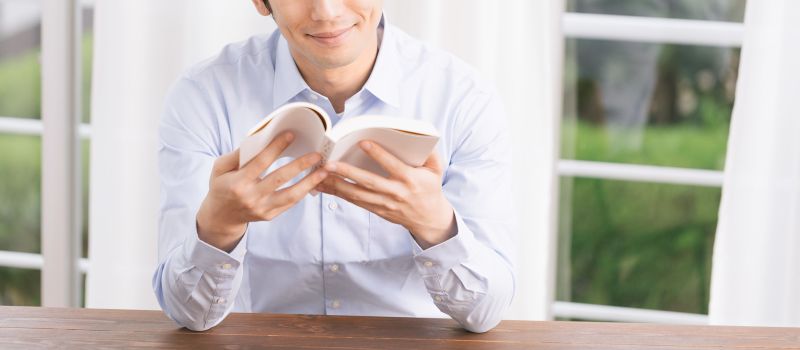
教科書では「ベンチ」の章だけが掲載されるため、全体のストーリーを知らない方も多いのではないでしょうか。
ナチス・ドイツで暮らすフリードリヒと父母のユダヤ人一家が描かれます。ナチスのユダヤ人迫害政策の影響で、一家は住居、職業、教育などで不利益をこうむり、さらにはナチスを熱狂的に支持した一般大衆からも、いわれのない差別を受けます。
大衆によるユダヤ人への嫌がらせが原因で母親は無念の死を迎え、父親はナチスに連行され、フリードリヒは一人ぼっちになります。
最後は、連合国がドイツへ激しい空襲を仕掛ける中、フリードリヒは差別されて防空壕に入れてもらえず、空襲が過ぎた後に主人公の僕は、彼が死亡しているのを発見する、という結末でした。
吾輩は猫である(夏目漱石)
二つめは、夏目漱石の「吾輩は猫である」です。
猫の吾輩がお世話になっている苦沙弥先生や周囲の人々、つまり人間界の騒動を、猫の目から皮肉交じりに眺めたお話です。(→「吾輩は猫である」の情報を見る)
教科書では、タイトルにもなった冒頭の有名なくだり「吾輩は猫である、名前はまだ無い」がある一章を中心に、中間部を抜粋して掲載されることが多く、この長編小説のラストを知らない人が多いでしょう。
主人公の猫は、人間が飲み残したビールをぴちゃぴちゃと舐めてしまい、なんと酔っぱらってしまいます。
そして、足元がおぼつかなく誤って水がめの中に落ちてしまいます。
何とか水から上がろうとあがくのですが、かめの縁までは距離があって難しく、後は現状を達観して死んでしまいます。
注文の多い料理店(宮沢賢治)
三つめは、宮沢賢治の「注文の多い料理店」です。
山に猟に来た主人公の二人が、そこに現れた西洋料理店に入り、数々の注文にこたえていくと...、というお話です。(→「注文の多い料理店」の情報を見る)

二人の紳士が次々と味付けされていくんでしょう?そして最後は助かる、それなら知っているよ、という方は多いでしょう。
確かに、扉の中から呼びかけられてあわや食べられてしまう一歩手前で猟犬が飛び込んできて、扉の向こうに突進します。それで助かります。
けれど、一番最後の最後、思い出せますか。
助かった二人の紳士は東京に帰りますが、その時に恐ろしさのあまり泣きまくってクシャクシャになった顔は、どうやっても元に戻りませんでした、というのが最後です。
はじめは兵隊のように身なりを整えて、手にはきれいな鉄砲を持って、鹿でも打ってやろうかと威勢が良かった二人が、最後には散々な姿になるところまでが作者の狙いですね。
ワニのおじいさんの宝物(川崎洋)
四つめは、川崎洋の「ワニのおじいさんの宝物」です。
鬼の子が川岸を歩いているとき、水ぎわで動かないワニを見つけます。死んでいるのかと思い、落ち葉を拾ってきて体の周りに積み上げていると、ワニのおじいさんが起きてお礼をする、というお話です。(→「ワニのおじいさんの宝物」の情報を見る)
ワニのおじいさんは、鬼の子のやさしさに感謝し、自分の宝物をあげようと隠した場所の地図を示します。宝物がなんなのかは教えてくれません。
鬼の子は地図をもとに、宝物のありかとされる崖の上にたどり着きます。
すると、そこからは美しい夕焼けが見られました。ワニのおじいさんの宝物はこの夕焼けなのだ、と鬼の子は納得し、いつまでも立ち尽くしました。
実は、今立っている足元に、本当に宝物を入れた箱が埋まっているとは知らずに。
どうぞのいす(香山美子)
最後の五つめは、香山美子の「どうぞのいす」です。
うさぎが小さないすを作り、「どうぞのいす」と立札を立てて大きな木の下に置きます。そこを通りがかったいろいろな動物が、次の方への思いやりの気持ちで食べ物を残していくお話です。(→「どうぞのいす」の情報を見る)
ストーリーは覚えている方も多いことでしょう。
ですが、どの動物が何を残したのか、最後は何が残ったのかは思い出せますか。
初めに来たのが、ろばさん、
初めに置いたのが、どんぐりの入ったかごでした。
ろばさんが昼寝をしているうちに、食べ物はどんどん入れ替わり、
最後にきたのが、りすさん、
最後に残したのが、くりでした。
ろばさんは、どんぐりが栗に代わっていてびっくり?!という温かいお話です。